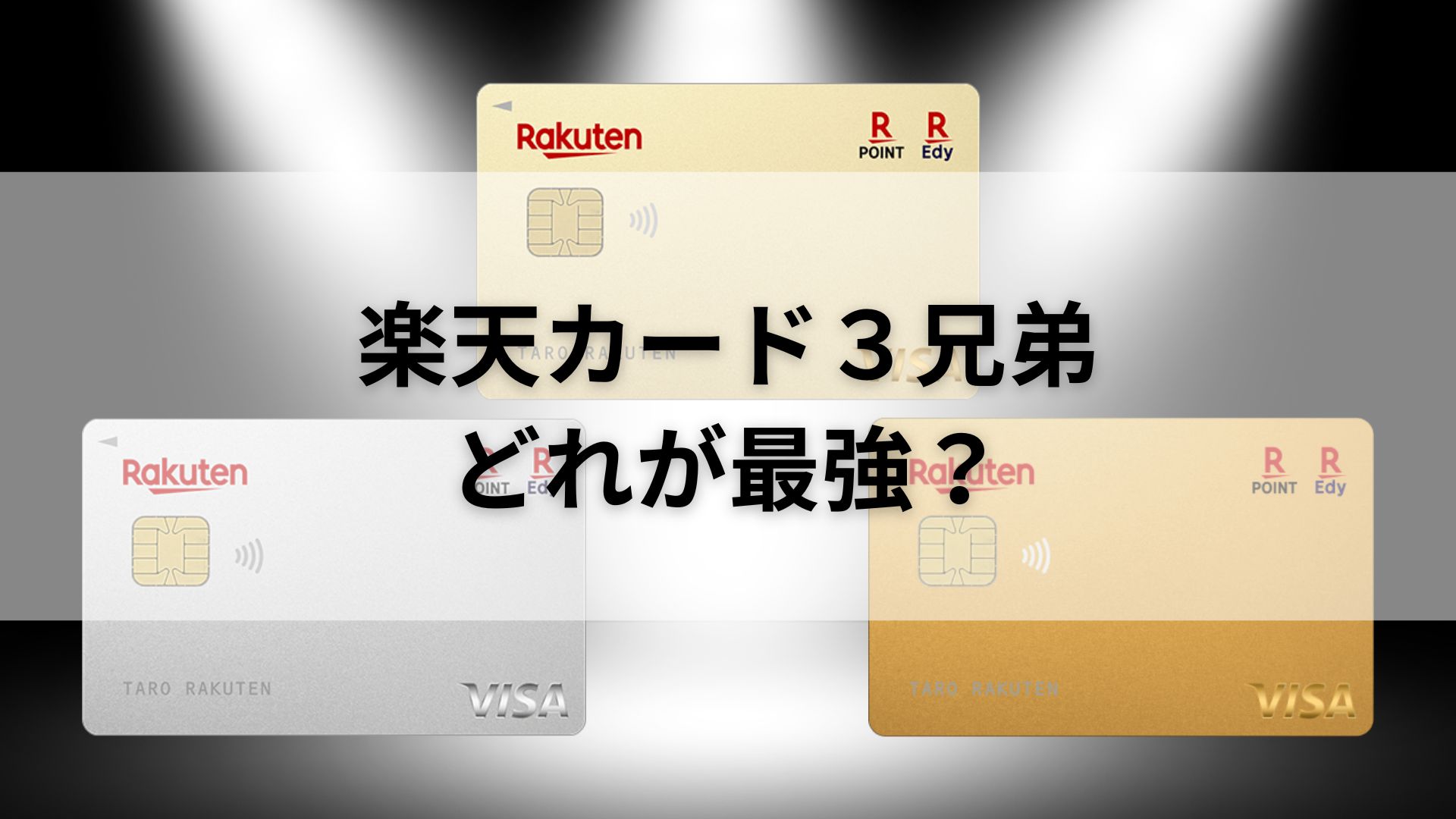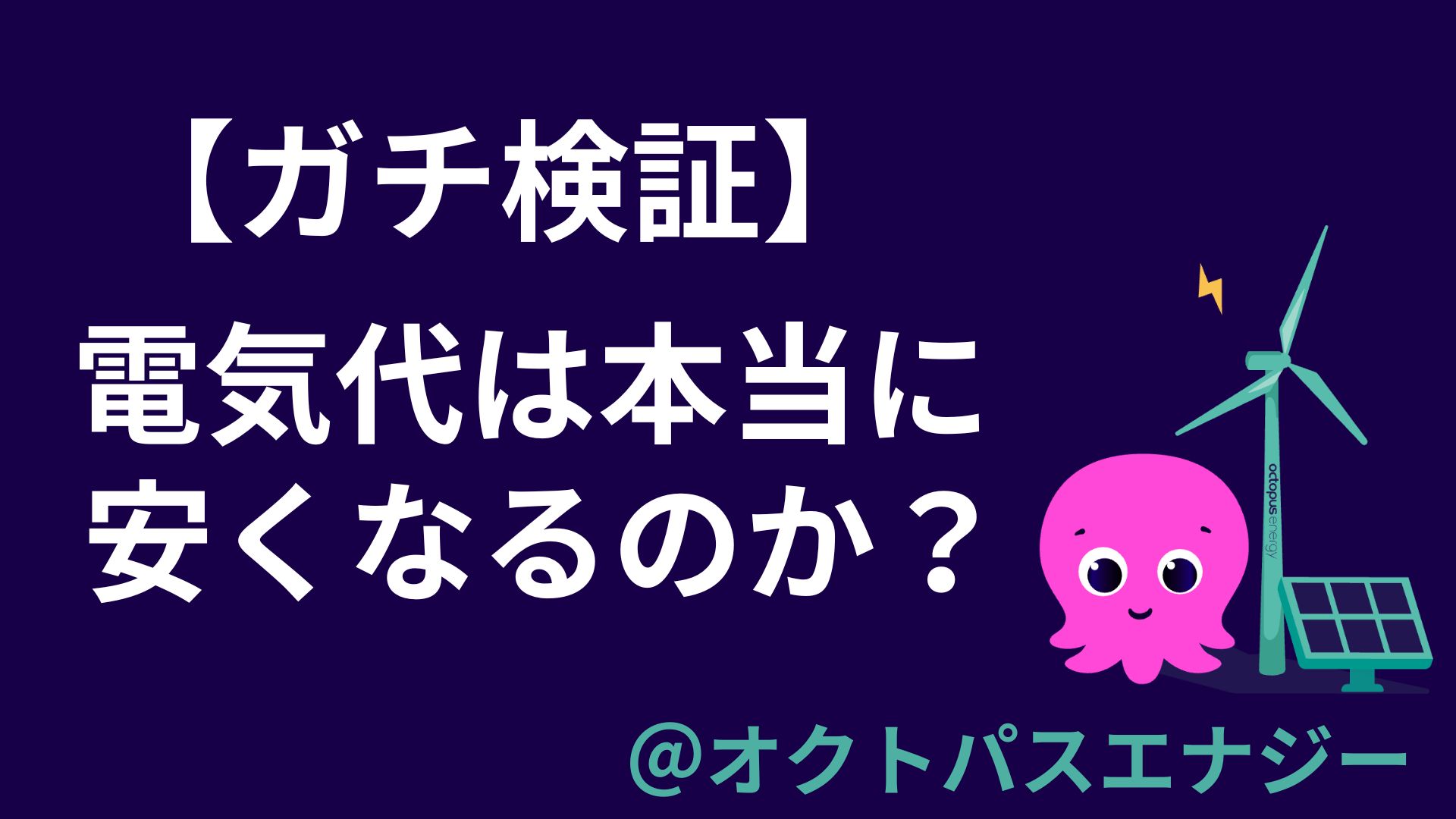子ども4人を大学まで育てるには総額いくら必要?リアルに試算してみた

リビングに転がる図鑑を囲んで「ねえ見て見て!」と無邪気に盛り上がる4きょうだい。親としては頬がゆるむ瞬間だけど、その背後では“学費モンスター”がゴゴゴ…と迫っている。
ざっくり言えば、公立オンリーで進んでも大学卒業までに1人800万超、4人なら3千万突破コース。しかも冬の電気代やスマホ代が爆上がりする現実まで加われば、家計はもはやボス戦。
いったいいくら準備すればこのラスボスを倒せるのか――今回はその数字と攻略法を、笑えるくらいリアルにさらけ出していく。

幼児~高校まで、ざっくりいくら?(※公立オンリーで試算)
「子育てってお金かかるって聞くけど、実際いくら飛んでくの?」
そんな疑問にドンピシャな最新データが文科省の調査(令和5年度版)。難しい数字をそのまま並べても眠くなるだけなので、中学生でも一発で理解できるように “おサイフ直撃表” にしてみた。
| 学年ゾーン | 年間学習費(平均) | 通う年数 | トータル金額(大体) |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(年少〜年長) | 約18.4万円 | 3年 | 約55万円 |
| 小学校 | 約33.6万円 | 6年 | 約202万円 |
| 中学校 | 約54.2万円 | 3年 | 約163万円 |
| 高校 | 約59.8万円 | 3年 | 約180万円 |
| 合計(幼〜高) | 約600万円 |
チェックポイント
・“給食があるから小学校は安い説”は半分ホント。だけど学年が上がるほど教材費・部活費でじわじわ上昇。
・高校は授業料無償化の恩恵があっても、制服・模試代・修学旅行で財布が悲鳴。
「大学まで行くと、結局いくらなの?」問題
さぁ、ここからがラスボス。日本政策金融公庫のシミュレーションで見ると、国公立大学4年間に必要な学費の平均が約248万円。入学金と授業料だけでこれだから、サークル費や食堂ラーメン代は別腹(死)。
| 内訳 | 初年度 | 2年目〜4年目(年額) | 4年間トータル |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 28.2万円 | — | — |
| 授業料 | 53.6万円 | 53.6万円 | 約214万円 |
| 合計 | 約248万円 |
こうしてみると、公立幼稚園から国公立大学卒業まで 1人あたり約822万円コース。
もし4人全員がこのルートを歩むとなると、ざっくり3,300万円超。私立や留学を挟めば福沢諭吉学園状態になるので、親としては震えるしかない。
まとめると…
- 幼児〜高校(公立)で約600万円
- 大学(国公立4年)で約248万円
- 合計 約822万円/1人
これが“理想的に安く抑えた”シナリオ。
リアルでは模試代や塾代、スマホ代で上振れするので、「最低でも800万、余裕を見て1,000万」 が安全圏。
こう聞くと絶望的に見えるけど、次の章からは「あ、これならやれるかも」と思える打開策をちゃんと用意してあるので、諦めずにつづきをどうぞ。
4人分まとめると、家計が軽トラで壁に激突するレベル
先ほど「1人あたり約822万円コース」と書いたが、これを4人に掛け算すると約3,300万円。もうこの時点で目がチカチカする。
しかも別ソース(某家計シミュレーター)では「幼稚園〜高校オール公立、大学は国公立」でも約4,295万円という数字を叩き出してきた。
どっちにしてもウン千万の世界で、桁が一つ増えるだけで胃がキューっと縮む。ここに私立や留学なんて夢をブチ込んだ日にゃ、「4人で1億円突破だって? ハハハ、笑うしかないね」と開き直るしかない。
「でも実際いつ、いくら出ていくの?」を可視化するとこうなる。中学生でも分かるように“ライフイベント×お金表”を置いておくので、深呼吸してからスクロールどうぞ。
| 子ども | 高校入学 | 高校卒業 | 大学卒業 (国公立想定) | 小計 (ざっくり) |
|---|---|---|---|---|
| 長男 (中1) | +2年 | +5年 | +9年 | 約822万円 |
| 次男 (小4) | +5年 | +8年 | +12年 | 約822万円 |
| 長女 (小1) | +8年 | +11年 | +15年 | 約822万円 |
| 末っ子 (年少) | +11年 | +14年 | +18年 | 約822万円 |
| 合計 | 約3,288万円 |
ツッコミポイント
- この試算は“理想的に安く抑えた国公立ルート”。私立を1人混ぜただけで+500〜1,000万円が上乗せされる。
- 4人の進学タイミングが絶妙に被ると、年間200万オーバーの学費ラッシュが発生する年も。財布のHPはゼロよ!
要するに、子ども4人=ミニバン1台ぶんの教育費が毎年エンジン全開で走り去るイメージ。これを聞いて「ムリゲー」と思った? 安心してくれ、次の章からは“どうやって資金をひねり出すか”というサバイバル術を全力投球で紹介する。ここでブラウザを閉じたらもったいないので、もう少しだけお付き合いを。
試算の前提と“なぜそんなにかかるのか”
今回の822万円/1人は、幼児〜高校を「全部公立」かつ大学を「国公立ストレート4年卒」の最安シナリオだ。ここには給食費・教材費・修学旅行費・部活遠征費・大学入学一時金・授業料4年分が含まれている。
まず前提をおさらいしておく。
一方、制服のお下がりや兄弟同じ塾に通わせての“兄弟割”など、個別の節約テクは入っていない。つまり「公的データで取れるベタ平均をそのまま合計した数字」と考えてほしい。
実際に家計簿を付けていると分かるが、学校配布のプリント代やPTA会費、部活の大会遠征の新幹線チケットなど、細々した臨時出費が毎月のように発生する。
正直、この822万円は“最低ライン”であって、リアルはもっと上振れするものと覚悟した方が心臓に優しい。
ダブル在学トラップ:兄弟が同時に大学生になったら家計が炎上する
ライフプラン表を横並びにすると見えてくる大問題が、「ダブル在学の重複ゾーン」だ。
例えば長男が大学4年、次男が大学1年になった年、ふたり分の授業料だけで年間100万円を超える。もし地方国立で下宿させるなら家賃+生活費で月10万円コース×2人=年240万円。授業料と合わせて年間350万オーバーが家計からドカンと抜ける計算になる。
さらに下の妹たちの塾代が重なるタイミングで、財布のHPはミリ残しどころか0表示。ここで親のボーナスカットや景気悪化が来たら本当に笑えない。
だからこそ、現金+奨学金+教育ローンのハイブリッド戦略で資金源を分散し、ダブル在学期のリスクに備えることが必須だ。
私立・留学・浪人で金額はどう暴れる? 想定外シナリオの破壊力
「うちは国公立オンリーで行く!」と親が鼻息荒く宣言しても、進学は子ども本人の意思と学力がカギ。
もし一人でも私立理系(初年度150万超)に進学すれば、4年間で追加400〜600万円は覚悟する必要がある。
さらに「1年浪人→私立」ルートは教材・予備校代も加算され、サクッと+200万円。留学を挟めば1セメスターで100万単位が飛ぶケースもざらだ。
結局のところ、1人あたり数百万円の“誤差”は“想定外”ではなく“あるある”なので、貯蓄は余裕を持って1.2倍〜1.5倍を見積もるのが安全圏というわけだ。
ここまでのまとめ
公立+国公立でも4人で3,300万円。私立や浪人が混じれば4,000万円超えは秒読み。
最恐イベントはダブル在学。年350万が飛ぶ年がある前提でキャッシュフローを組む。
想定外シナリオに耐えるには、**資金源の分散と“1.5倍見積もり”**が鉄則。
奨学金という“先行投資ローン”をどう使いこなすか
「借金は怖い」とビビる気持ちは分かるけれど、大学費用の山を前にしたら奨学金はほぼ必修科目。
日本学生支援機構(JASSO)の最新データでは、大学生の約半数が奨学金ユーザー。しかも平均借入額は300万円オーバーだ。
「300万?! 車買えるじゃん」とツッコミたくなるけれど、分割で払えば月1万〜2万円台に抑えられるケースも多い。重要なのは“借りたらすぐ返済シミュレーション”を家族で共有すること。
例えば無利子(第一種)なら4年間で240万円借りても金利ゼロ、卒業後15年返済で月1.3万円ほど。利子付き(第二種)でも金利0.6〜1%台なら、住宅ローンより低い。
要は「学費→給与で返済」というキャッシュフローを可視化し、子ども自身にも自覚を持たせるのがポイントだ。
国の支援アップデート:多子世帯は“授業料タダ”の神風が来る
2020年度からスタートした「高等教育の修学支援新制度」は、所得条件を満たすと授業料減免+給付奨学金がもらえる仕組み。
ここにきて**2025年度から多子世帯(子ども3人以上)の授業料・入学金が“ほぼ全額無償化”**という激アツ情報が追加された。
わが家のように4人いる場合、国公立なら年間約54万円×4年=216万円が丸っと消える計算。私立でも上限70万円程度まで免除される予定なので、「国公立しかムリ…」と肩を落としていた親御さんには朗報だ。
もちろん所得制限はあるが、夫婦合算年収およそ600万円台までOKという試算もあるので、対象になるかチェックしておく価値は大きい。
先取り貯蓄&祖父母パワー:自前の“教育ファンド”を育てる
とはいえ奨学金も支援制度も「後出し」か「条件付き」。一番堅いのは、児童手当+つみたてNISAをセットで“先取り貯蓄”する作戦だ。たとえば児童手当だけでも第3子以降は月1万円が高校卒業まで入る。これを年利3%想定の投信積立に回すだけで、18年間で約300万円に膨らむシミュレーションもある。さらに祖父母が「うちの可愛い孫に教育資金を」と肩を押してくれるなら、教育資金贈与の非課税枠1500万円を活用。
贈与税ゼロで学費口座にドンと入金できるので、奨学金の借入額をがっつり減らせる。要は「国の支援」と「自力の先取り」をゴリゴリ積み重ねていくのが、多子世帯の勝ちパターン。
――と、ここまで読んで「ウチの家計、固定費で手いっぱいなんだけど…」と頭を抱えた人もいるはず。そんなときは、まず電気代などの固定費削減から手をつけるのが王道。
最近話題のオクトパスエナジーで電気代を1万円/月下げられれば、年間12万円、18年で200万円超を教育資金にシフトできる。細かいテクはこちらの記事でチェックできるので、家計のムダ取りと同時進行で“教育ファンド”を育てていこう。
家計ダイエットは “まず固定費” から始めるのが王道
塾代も参考書代も削れない?だったら毎月ガッツリ出ていく家賃・光熱費・通信費・保険料を真っ先にシェイプアップするしかない。ここを削れば、浮いたお金をそのまま教育費口座にスライドできるからだ。
実際うちの8人家族も、冬の電気代が「もはやボスキャラ級」に跳ね上がったのを機に本気で固定費を見直した。
家賃は更新時に管理会社と交渉して月3,000円ダウン、スマホは日本通信SIMで夫婦2台まとめて月8,000円ダウン。交渉・乗り換え・プラン変更──この3ワードだけで年間十数万円がポンと浮いた。もはや「節約というよりガチャの当たり枠」を引いた気分である。
電気代を一刀両断するなら “タコ” に乗り換えろ
光熱費の中でも特にデカいのが電気代。そこで登場するのが オクトパスエナジー。
基本料金ゼロ、しかも再エネ100%という“地球にも財布にも優しいタコ”。ウチも試算したら、夏冬のピーク月で1万円近く下がる見込みだったので、もはや「やらない理由が見つからない」状態。
気になる人は、後でこっそり → 電気代を節約する具体的な流れはこちら をチェック。広告っぽさゼロで、手続きやメリット・デメリットを赤裸々に書き倒しているので安心してどうぞ。
浮いたキャッシュは “教育ファンド” へ即送金
固定費が月1万円削れたら、その1万円を翌月から自動積立へ回す。
ジュニアNISAや学資保険でもいいし、ただの定期預金でもOK(大事なのは「生活費口座に残さない」こと)。
たかが月1万でも18年積み立てれば216万円+利息。4人分なら合計800万円に手が届く計算になる。つまり、固定費カットは教育費の先取り貯蓄装置なのだ。
教育費の試算で「うわ、3,300万とか絶対ムリ…」と青ざめたそこのあなた。まずは電気・スマホ・保険の見直しで家計をスリム化し、その脂肪(=ムダ金)を教育ファンドへ移植しよう。
節約は筋トレと同じで、やった分だけリターンが出る。将来、子どもたちが学費の心配なく好きな進路を選べるように──まずは固定費ダイエットで家計に呼吸スペースを作ってあげよう。